| 脚と鐙と拍車 | |
| 鐙の踏み方 | 脚の使い方 |
| 鐙の踏変え | 鐙革の調整 |
| 拍車の使い方 | |
正しい鐙の踏み方は、前足底を鐙にかけて靴底を水平にした状態。
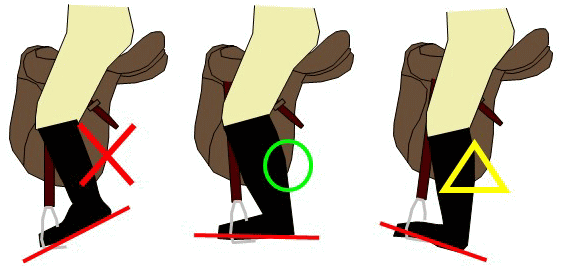
この絵の真ん中緑の丸を付けた状態が正しい踏み方。左側のように踵があがっていたり、あるいは、右側のように下がりすぎていたりすると、踝は柔軟に動くことができない。それに、踵があがると脚の前後位置が後ろ過ぎ、踵が下がりすぎだと脚位置は前過ぎとなって、正しい前後位置を保てないことが多い。
左端のつま先下がりの絵は、鐙に足先を載せて踵が浮いた状態だが、こういうつま先下がりはよほど鐙が短く無い限りなりにくい。普通は、鐙に深く脚を突っ込み過ぎて、つま先下がりになっていることが多い。
初心者が思いきり踵を下げたつもりになっても、端から見れば、水平より多少踵が下がっている程度のことが多い。だから、最初は下げすぎなど心配せずに、思いきり下げるつもりで乗らないと、靴底が水平にはならない。なので、最初は「つま先下がりは絶対ダメ」とだけ意識すれば良い。
で、馬が常足など上下動の少ない動きをしている限りは、初心のうちでもだいたいは鐙に正しく足を乗せておくことができる。悩ましいのは、速歩や駈足など動きの激しい歩様になったとき、鐙の中で足が踊って、鐙に足を深く突っ込みすぎたり、甚だしい場合は鐙から足が抜けてしまったりする。もちろん、水平になんかしていられない。
鐙に乗せた足は踵をショックアブソーバーにして、このアニメのように(多少動きを誇張してあるが)足首を柔らかく乗れなければいけない。これができれば、鐙の中で足が踊ったせずに済み、鐙に足を突っ込みすぎたり、鐙から足が抜けてしまうようなことが無くなる。
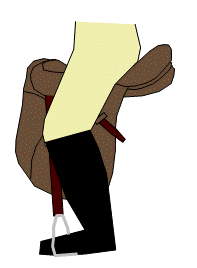
これは難しい(数年経っても出来るようにならない)のだが、実はそれほど難しくもないのかもしれない。というのは、「乗馬をならい始めて何年もたつのに、足が鐙の中で踊って恥ずかしい。なんとかならんかしら」といつも踵をクッションに使うことを意識して乗るようにしていたら、数ヶ月でできるようになった。だから、鐙の中で足が情けないことになっていることに気がついた時だけ「あれっ、まずい。踵のクッション」なんてことではダメで、馬がなんらかの運動をしている間中「踵のクッション」を強く意識して、上のアニメのように踵を動かすことを意識的に実行すれば、比較的簡単に身につくことを知った。足が下がるときに、クッションを意識して「柔らかく」踵をしっかり押し下げることがコツかな。
ところで、「踵を下げよう、下げるんだ」と意識するより、「つま先を引き上げるんだ」と意識する方が、踵を下げ易いかもしれない。それに、つま先を引き上げると考えて脚扶助を使ったほうが、踵を下げる効能が実感できる。
・つま先を引き上げる(踵を下げる)ことの効能
(1)脹ら脛が硬く突き出ることで、この突き出た部分で馬腹を、強固に圧迫して強い扶助を送ることができる。
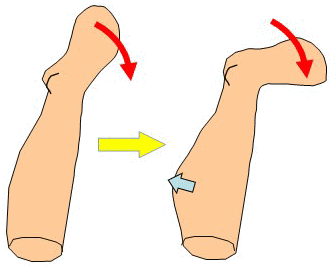
足を空中に浮かして自分で触ってみると、人間の脹ら脛部分は、柔らかくて、ここを使って馬腹を圧迫してもふにゃふにゃとクッションで押しているようでいかにも圧力が伝わりにくそうだ。(上の絵の左側)
けれども、足の甲をスネの方に引きつけて、脹ら脛に触ってみると、脹ら脛が硬く出っ張っるのが解る。(上の絵の右側、青い小さな矢印部分)この固い出っ張りで圧迫すれば、しっかりとした強い力を伝えられる。馬に跨がってこれをやってみれば、脹ら脛の出っ張りで圧迫することの強固さが体感できる。
鍛えた馬術競技者だと、脹ら脛は2cm以上は固く突き出る。脚で締め付けずとも、足の甲を引き上げるように力を入れて脹ら脛の筋肉を固く突き出させることで馬に指示を出せるという。
(2)脹ら脛部分で馬体を挟んで締め付ける強い力を出せる。
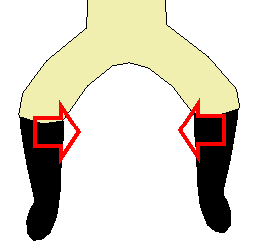
この絵のように、つま先を下げて鞍に跨ると、脹脛で馬体を挟んで圧迫する力を出しにくい。
つま先を下げた姿勢では、力強い脚の扶助が出せないことが判る。
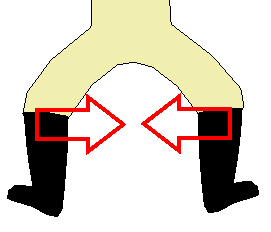
しかし、この絵のように、つま先を引き上げておくと、馬体を圧迫する方向に強い力を出すことができる。
不思議だが、つま先を下げた場合に比べ、踵を下げた方が脚で馬体を挟む力を強化できる。
・効果的な脚の力の入れ方
インストラクターに「もっと脚を使って」とか「全然脚が効いてませんよ」などと言われても「こんなに頑張って力いれてるのに」「もうこれ以上力出せっても無理」とか思う人はこちらを見てください。
・鐙を踏む位置
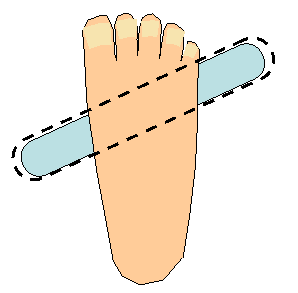
直角に踏まず、足の横幅のもっとも広いあたりに、斜めに足を掛ける。
鐙に深く足を突っ込むと踝がショックアブソーバーとして働き難くなる。それに、落馬したとき足が鐙から抜けず、馬に引きずられたりして大変危険。足は必ず浅く掛けなくてはいけない。
ただし、障碍を跳ぶときはしっかり鐙を踏みしめるために、多少深く履いてもよいという。
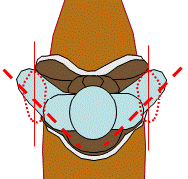
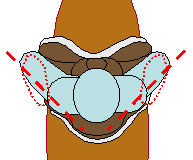
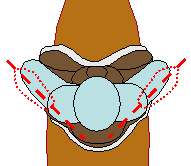
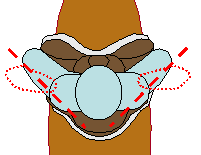
・まとめ
良い踏み方
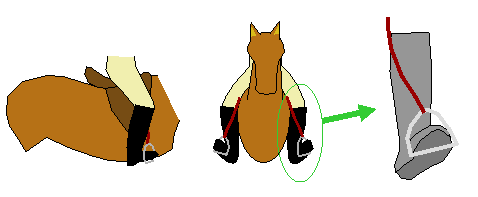
鐙には浅く足を掛けて、親指側に重さを載せる。
つま先をやや開いて膝頭方向に引き上げ、足の裏の親指側で鐙を踏む。親指側で乗ることがとても大切。靴底は水平が良くて、この絵は踵を下げすぎ。けれども、これくらいが良いんだと意識して乗らないと、踵があがっていることが多い。
悪い踏み方
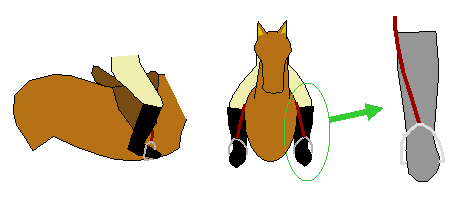
踵が上がると どうしても鐙に深く足を突っ込むようになるし、脚扶助を上手に使えない。
また、こういう鐙の踏み方だとどうしても上体が前屈みになりがちで、馬のちょっとした不規則な動きで落馬しやすくなる。
 馬の推進力は、脚による扶助から生まれる。そして、推進力がなければ、ハミ受けもできないし、馬術的にきれいな動き(後肢を踏み込んで体重を支える)ができない。だから、脚の使い方はとても大切。
馬の推進力は、脚による扶助から生まれる。そして、推進力がなければ、ハミ受けもできないし、馬術的にきれいな動き(後肢を踏み込んで体重を支える)ができない。だから、脚の使い方はとても大切。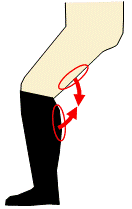
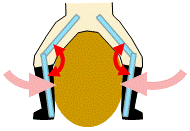
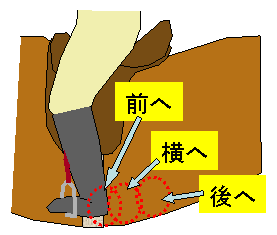
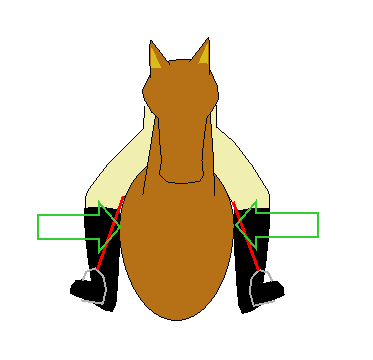 ふくらはぎ(脹脛)の内側やや上部を使って馬の腹(左の絵の緑の矢印部分)を圧迫して馬に推進を指示。つま先を上げたときに固く出っ張り出す脹ら脛の膨らみを押し当てて圧迫する。
ふくらはぎ(脹脛)の内側やや上部を使って馬の腹(左の絵の緑の矢印部分)を圧迫して馬に推進を指示。つま先を上げたときに固く出っ張り出す脹ら脛の膨らみを押し当てて圧迫する。・馬を曲がらせるための脚の使い方
馬を曲がらせる場合、基本は体重と脚による扶助を主として、手綱による扶助は補助的に考える。曲がらせようと手綱に意識が集中すると、推進が弱くなって、馬が内側に切れ込んだり外側にふくらんだりするから、曲がっている時も脚扶助を効かせて推進を心がけなければいけない。
一般的には、内方脚を主に使って曲がらせる。しかし、内方脚でなく外方脚で曲げよという方法もある。内方手綱で馬の首を曲がる方向へリードし、外方脚で蹴る(圧迫する?)方法がこちらに紹介されている。どちらが正しいのかは判らないが、どちらにせよその馬が調教されたやり方でないと曲がってくれないことはたしか。
左足(外方脚、回転外側の足)は普通の位置よりも後方に引く、とたいていの教本に書いてある。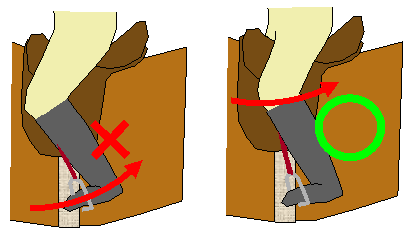 H先生に、「外側の脚を引けというのはこんな具合でいいんですか?」と左のバツを描いた絵のように踵を後ろに振って脚を後ろにずらせたところ、それは違うといわれた。
H先生に、「外側の脚を引けというのはこんな具合でいいんですか?」と左のバツを描いた絵のように踵を後ろに振って脚を後ろにずらせたところ、それは違うといわれた。
で、教わったのが右の丸を描いた絵のように太ももぐっと引いて腿全体を(膝も含めて)後ろにさげる方法。外方脚だけを意識してこれをやろうとしても、股関節が硬いとなかなか難しい。
なので、お勧めは、「(内方の腰を斜め前に出し)内方脚で段を一段降りる」というRRに紹介されているやり方。これで、体重による扶助も出来るし、外方脚は自然に後ろへ引かれる。内方の鐙を踏み込む力で内方脚による圧迫も自然にできる。
RRによれば、内方脚による圧迫と外方手綱による半減却の扶助によって(内方脚圧迫と外方手綱を控えるを短時間に、馬の肢の動きに合わせて、交互に繰り返すことで)馬に内方姿勢を取らせることができるという。そしてこれが、斜体扶助という魔法の杖になるらしい。
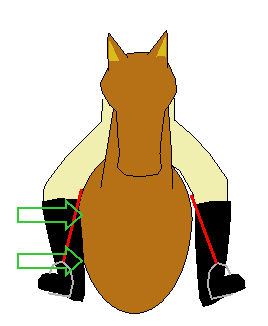 普通に脚が置かれている位置を前後させずに、腹帯のすぐ後ろを圧迫するのがよいという教本もある。
普通に脚が置かれている位置を前後させずに、腹帯のすぐ後ろを圧迫するのがよいという教本もある。 最初の頃は、鐙に浅く足をかけていても、いつのまにか鐙が深くなってしまう。
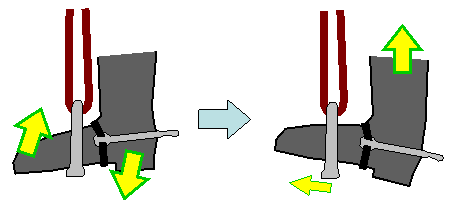 大体は、いつの間にか鐙に足が深く入りすぎってしまう。これを直すには、この絵のように踵を下げてつま先を上げる。そうしておいて、足を、後ろに引くのでなく、上に持ち上げて鐙から足を浮かせる。
大体は、いつの間にか鐙に足が深く入りすぎってしまう。これを直すには、この絵のように踵を下げてつま先を上げる。そうしておいて、足を、後ろに引くのでなく、上に持ち上げて鐙から足を浮かせる。
すると鐙は足から離れてぶらぶらの状態になり前後に自由に揺れて、これで自然と鐙は足から抜ける方向、踏み込みが浅くなる方向へ動く(小さな黄色の矢印)。
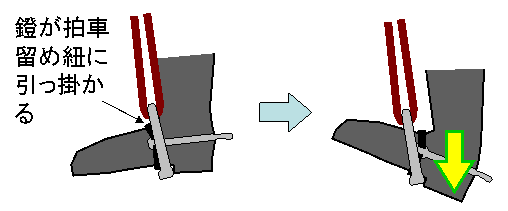
時々、あまりに鐙への踏み込みが深くなってこの絵のように拍車ベルトや留め金具に鐙が引っ掛かって足が抜けなくなることがある。このような場合は、上に説明したやり方では抜けない。
絵の右側のように、踵を無理やり押し下げることで鐙の上部と足の甲との間に隙間をつくり、引っ掛かっている拍車ベルト(留め紐)などを外す。
引っ掛かりが外れたら、先に説明したやりかたで踏み込みを浅くする。
鐙革の長さは乗る前に調整しておく。
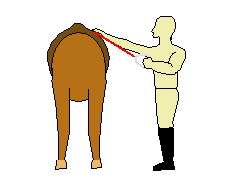 馬の脇に立って 片手の指先を鐙革を止める留め金(鐙革托鐶)に添えて、もう一方の手で鐙をもって脇のしたに当てたとき、脇の下まで鐙がピンと張って届けばちょうど良い長さ。
馬の脇に立って 片手の指先を鐙革を止める留め金(鐙革托鐶)に添えて、もう一方の手で鐙をもって脇のしたに当てたとき、脇の下まで鐙がピンと張って届けばちょうど良い長さ。
調整している間に馬が動いてどこかに行ってしまわないように、伸ばした右手を手綱の輪にとおしておくか、あるいは、左手で鐙といっしょに手綱をにぎっておく。
馬の乗り降りには左側の鐙を使うので左側の鐙革が右よりも伸びてしまう。このため、左右同じ番号の穴でも長さが違ってきたりするから、ときどき鐙革の左右を入れ替えるとよい。
障害を跳ぶ場合は通常より短くして、鐙の上に立って腰を浮かせたときにお尻と鞍の距離を充分に取れるようにしておく。
馬に乗ってから調整する場合は下の図のように調整する側の脚を前にずらせて 片手で鐙革を引き上げて調整。調整後は 鐙革のバックルが鞍の鐙を留める金具(鐙革托鐶)にしっかりと密着するように戻しておく。きちんと戻っていないとその部分が出っ張って内股を擦りむくことがある。脚を後ろにずらせて 脚の前に鐙革を引っ張り揚げて調節する というやり方を見たことがあるが 前と後ろ どちらにずらせて調節するのが良いのか判らない。
余談だが、日本では「鐙を短く」とか「長く」とか言うが、英語では「longer(長く)、shorter(短く)」ではすぐには通じない。「higher(高く)、lower(低く)」と言う。発想の違いがあって面白い。
| 鐙革の長さの調整 | 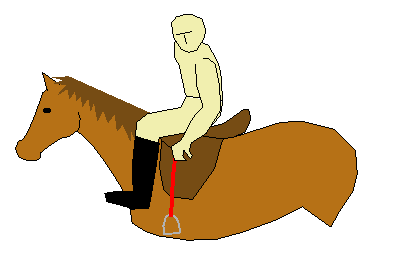 (1)鐙革の余っている部分を引き抜いて (1)鐙革の余っている部分を引き抜いて(2)上方へ引っ張ってバックル部分を鞍の留め金から引き上げ、バックルのピンを外して (3)バックルを前後させて長さを調節し、バックルのピンを鐙革の穴に通して長さを固定。 (4)バックルを鞍の留め金(鐙革托鐶)にぴたっと張り付くように戻し、余った鐙革をもとのように戻す。 |
| 手順 | 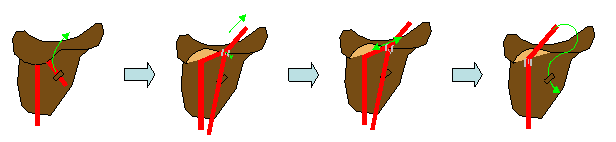 |
鐙革の長さを調整後は、上の(4)の説明のように、バックルを鐙革托鐶にピタリとはまり込むように戻す。普通は、鐙革の内側(鞍に近い側)を手で押し下げて戻す。ところが鐙革が分厚く硬い場合には鐙革托鐶と鐙皮のすべりが悪く、手の力では押し下げられないことがよくある。こんな場合は、手ではなく足の力を使う。
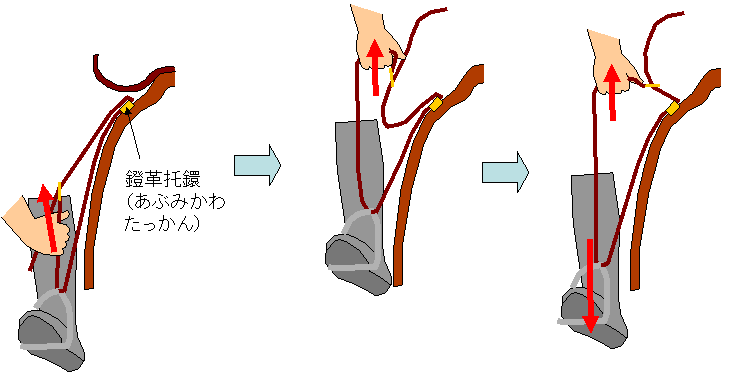
右足の鐙を戻す例を前から見たもの。
右足の膝を緩めて鞍から離して、膝の内側に右手を下して、鐙革の外側(鞍から遠い側)の鐙革をバックルのしたの部分を右手で親指が上を向くように握って大きく上に引き上げる。右足は鐙に掛けたまま、真ん中の絵のように軽く持ち上げ。
次に右手は鐙革を引っ張り上げたまま、右足で鐙を強く踏みおろし、足の力で鐙革の内側を引き下ろす。手の力よりも数倍大きなあしの力を使うので楽にできる。
バックルが托鐶にぴたりとはまり込むまでこの操作を何回か繰り返す。だいたい二回ほどやればピタリとはまる。
![]() 馬によっては拍車を嫌って、拍車を当てると尻っぱねをしたりするものもいる。こういう馬に拍車を外して乗っていたら「拍車はどうしたの?」「嫌うようなので外しました」「ちょっと反抗されたぐらいで、弱気に外してどうするの。そのくらいは押さえ込んでしまえなきゃだめだよ」とI先生に言われたことがある。
馬によっては拍車を嫌って、拍車を当てると尻っぱねをしたりするものもいる。こういう馬に拍車を外して乗っていたら「拍車はどうしたの?」「嫌うようなので外しました」「ちょっと反抗されたぐらいで、弱気に外してどうするの。そのくらいは押さえ込んでしまえなきゃだめだよ」とI先生に言われたことがある。
拍車を嫌がってちょっと跳ねられたら、拍車を使うのを遠慮しする。これは、跳ねればいやなことから逃れられると馬に教えていることになり、人の手に負えない癖馬に育てているのと同じこと。反抗は押さえ込んで、指示を貫徹させなければいけない。
とはいえ、跳ねられても「コラ、逆らうんじゃない」と拍車を使い続けられるにはちょっと技量がいる。だいたいは「これりゃあ危ない、落とされるかも」とビビッて馬の言うことを聞いてしまうから、拍車や鞭に反抗して尻っぱねをする馬はけっこうあちこちに居る。
外乗などでは、拍車が強くあたるとすっとんでいく可能性もあり危険だということで、外してくれと言われることが多い。
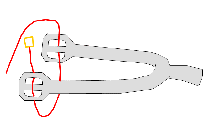
普通の拍車には左右の違いは無く、左右同形。
棒状の拍車などでは上下の向きの違いがあり、拍車の棒の部分が、左の絵のようにやや下を向くようになるのが正しい装着方向。
拍車革は、乗馬のガイドライン第一巻によれば、この絵のように通す。
装着位置は踵から指4,5本分上の高さのところ。長靴などに拍車台がついていれば、台の上に固定させればだいたいはその位置になる。拍車は水平に取り付けなくてはいけない。
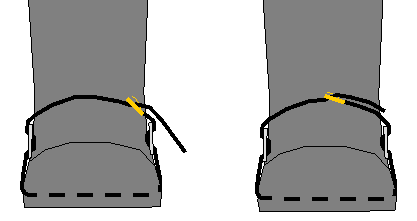 これは 左足に装着した拍車を前から見た絵
これは 左足に装着した拍車を前から見た絵
左側のように留め金が拍車に近くなりすぎると、足を鐙に突っ込み過ぎた(鐙が深くなり過ぎた)ときに、鐙に拍車の留め金具が引っ掛かって足が鐙から抜けなくなる可能性があって危険。
右側のように留め金具が足の甲よりになっていると、鐙に引っ掛かる可能性が低い。
 これは左足に装着した拍車を左後方から見た絵
これは左足に装着した拍車を左後方から見た絵
この絵のように、金具(小さなバックル)を締めて、余った部分が体の外側(この絵では左側)に垂れるようになっていなければ左右が間違っている。
危険防止のためと、出っ張った金具などで馬体を傷つけないように、金具の類が外側にくるようにする。身につけるものの左右が判らなかったら、この原則で。
叱るために使う場合以外は、拍車は強く当ててはいけない。気が付かないうちに拍車が強く入ってしまうことを避けるために、慣れないうちは、拍車の棒は短めのものを選んだ方が無難。私の乗り方を見てI先生は、拍車を棒の長さのもっと短いものに代えた方が良いコメントをくれた。ちなみにその時は上の絵のような棒拍車の長さ3cmのものを使っていた。一番短い1.5cmのもので良いのだと思う。
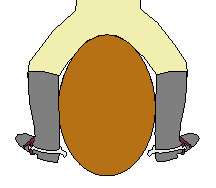 拍車をつけての騎乗を後ろから見た絵。
拍車をつけての騎乗を後ろから見た絵。
特に鐙革を短くしたりしていなければ、足先を多少開いても、拍車は馬体に触れることはない。
これで拍車があたるようなら短い拍車に代えた方が良い。
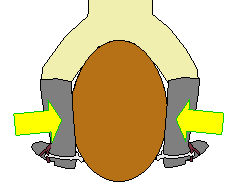 拍車を使う場合は、このように脹脛をグッと締めて拍車が馬腹に触れるようにする。
拍車を使う場合は、このように脹脛をグッと締めて拍車が馬腹に触れるようにする。
強く当てる必要はなく、脹脛の締め加減で、拍車が馬腹に触れているかいないかが判るようにならなければいけない。
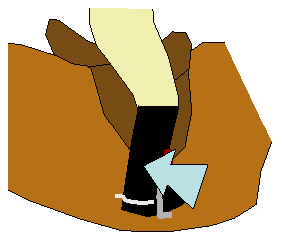 上の絵を横から見たもの。
上の絵を横から見たもの。
足首を動かさず、脹脛から踝を使って馬腹を圧迫することで拍車が馬腹に当たるようにする。
 これは、I先生に習った方法で、拍車は下から擦りあげるように使う。
これは、I先生に習った方法で、拍車は下から擦りあげるように使う。
この方法だと、推進しようとすると踵が上がってしまうことが癖になる心配があるが、こう使えと書いてある本は多い。
ただし、欧州の教本には、拍車は突き刺すように鋭く使えと書いてあるものが多い。
| この馬だと足をダランと下げると拍車は馬腹にあたらない。この動画は昔のもので、当時は踵を下げる意識がそれほど無かった。それに裸馬で踵を下げておく筋力も無かった。 |